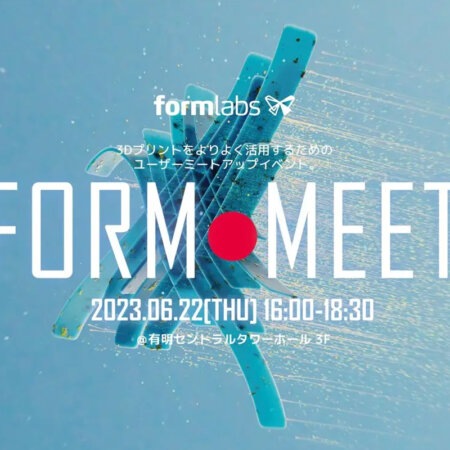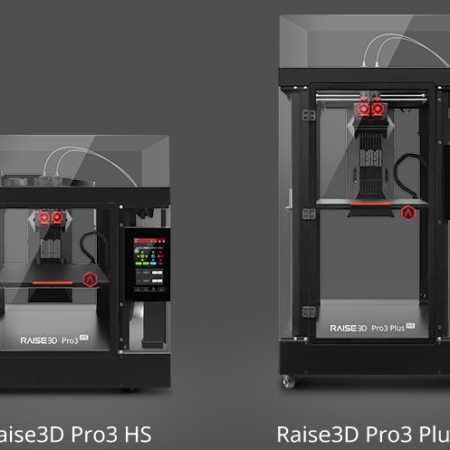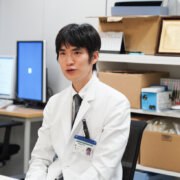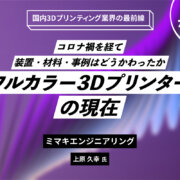TCT Japan 2025 主催者セミナー参加報告

2025年1月29-31日に東京ビッグサイトを会場に、日本における最大級のAM(アディティブ・マニュファクチャリング)総合展示会「TCT Japan 2025」が開催された。シェアラボでも開催前から複数の記事やYouTubeチャンネル「ShareLabTV」でお知らせをしてきたが、ここでは、会場内メインステージで3日間にわたり開催された主催者セミナーでの講演内容の重要なポイントをまとめてお伝えする。(写真は開会挨拶をするRapid News Publications Ltd.のDuncan Wood氏 主催者の許可を得て記者撮影)
TCT JAPAN 主催者セミナー概要
メインステージでの講演プログラム詳細は展示会ウェブサイトを参照いただきたい。全講演事前聴講予約制、毎回完全入れ替え制で行われたが、100名以上の座席が足りず、立ち見が出る講演が多数あり、来場者のAM関連情報に対する関心が高まっていることが伺えた。拝聴した講演の中から、3つの分野に分けて重要なポイントを以下にお伝えする。
国内外のAM市場動向
まず本展示会共同主催企業であり、世界5か国・地域で展示会、カンファレンス、雑誌を展開する「The TCT Group」をグローバルブランドとして有するRapid News Publications Ltd.のDuncan Wood氏から、この展示会が株式会社JTBコミュニケーションデザイン社との長年の協力関係により開催されていることや、日本のAM市場の発展には大きな期待を寄せているとの開会挨拶があった。
世界的なAM市場動向については、CONTEXT社(イギリス)Global Analysis and Research Vice Presidentの Chris Connery氏から、同社は13年間、毎四半期ごとに世界で企業調査分析しており、その2024年第3四半期までの最新結果概要が紹介され、プリンター、材料、サービス全体として5年平均年率+12%成長しており、特にプリンター価格分類でエントリーレベルが急伸する一方、その上のプロフェッショナル、ミッドレンジ、インダストリアルではマイナス成長の傾向にあり、中国の成長率もマイナスに転じ、全世界で苦戦しているとのこと。2025年はエントリーレベルの成長は鈍化、上位3分野は緩やかな回復を予測していたが、講演後に直接尋ねたところ、アメリカの関税の行方などに左右されることから、予測は難しいとのことであった。
国内のAM市場動向については、株式会社矢野経済研究所 小山 博子氏からは、日本のAM市場全体として、当初の予測より低い成長率が続くものの、中小企業でもCAD/CAMの普及が進んで、最近の傾向として補助金の活用などで同種または異種の3Dプリンターを複数所有する企業が増えており、一方低成長の課題はデジタル人材の育成であり、大企業は採用や社内育成、中小企業は社外サービス利用での解決傾向にあるとのこと。また最近、中小企業でも大学や公設試との共同開発例も増え、今後前向きな企業が増え、成長に期待するコメントがあった。次に株式会社みずほ銀行 秋山 紀子氏からは、AMに対して海外では今までになかった画期的な新製品を作るためのツールという認識が広がり、日本でのみ、AMの量産品への活用の着意が遅れることの懸念を示した上で、課題の高コストに対し、DfAMの活用が重要で、国内でも好事例が出てきたり、昨年からの新しい政策もあり、DfAMを起点とした日本のものづくり革新への期待と、挑戦した結果出来なくても、いつもと違う角度から設計を見直すことで、製品の画期的なバージョンアップへつながり、企業としてのポテンシャルが上がるという利点を含め、積極的な取り組みへ提言があった。また既にシェアラボでも報じた、みずほ銀行が公開している「日本の製造業における金属AM活用の重要性~DfAMを起点とした日本のものづくり革新~」の紹介があった。
国内外のAM活用動向
海外からの講演者として、Google社(アメリカ)Pixel事業でのテクニカルプロジェクトマネーシャーであるAnne Pauley氏から、スマートフォンなど同社製品開発工程における樹脂3Dプリンターの活用状況と効果について、日本で初めての講演があった。製品開発の流れの中で、最初かつ最も長い、7か月から1年の「開発」で最も3Dプリンターを活用しており、それは限られた期間に多くの繰り返し検討(イテレーション)を行うからであり、デモンストレーションや責任者承認を得る、またはチームの統一性とデザイン方向の共有に効果が高く、また続く各開発工程の中で多種多数の3Dプリンターや材料を目的により使い分けているとのことであった。3Dプリンターは、開発のスピード向上は当然であり、品質でも、検討サイクル増で不具合を削減し、高品質は高収益へつながること、コストも開発初期の挑戦は安価だが、後になるほど高価になり、開発重要な、ユーザーに実際使ってもらうテストにも有効であるとも述べた。今後は試作品がもっと製品に近づけるか、補修部品やカスタム製品に使えるかに期待しているそうだ。講演後個別に伺ったところ、3Dプリンターはスピード重視のため、全て社内で市販の小型プリンターをそのまま使っているとのことで、世界的大企業でも特別なことはなく、性能に課題があっても市販品を適切に使い、十分な活用効果を出していることが分かった。
その他Satellite Applications Catapult社(イギリス)からは、人工衛星や宇宙ステーション、月面などで補修部品などを製造する研究開発へのAM活用、またTapestry, Inc. 社(アメリカ)からは、自社所有ブランドCoach, Kate Spade, Stuart Weitzmanの製品開発において、3Dプリンティングは世界中の開発者、デザイナーと工場のコミュニケーションギャップを埋めるとし、変化の速いファッション市場において、従来型を使った試作から大幅なコストと期間の削減だけではなく、流れの良い製造、低汚染、サステナビリティへの貢献の利点があると述べるなど、AM活用分野の幅広さを再認識する講演があった。
国内からも株式会社SUBARUから、カーデザインにおけるAM活用の現状と課題、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)から、大型ロケット構造へのAM適用を目指し、国と民間企業が連携して取組む研究開発事例、またセレンディクス株式会社と株式会社JR西日本イノベーションズから、「セレンディクス3Dプリンター住宅」の最新動向と、古い無人駅舎を列車運行を止めずに、地域に合ったデザインで愛される駅舎を建てるプロジェクトの紹介などがあり、国内でも幅広い産業でAM製造活用への取り組みと課題を知る貴重な講演があった。その中で特にコニカミノルタ株式会社の講演では、業務用プリンター開発製造事業において、2019年に樹脂レーザーPBFプリンターで社内試作を始め、DfAM研究実践、少量生産機種の部品製造への適用から、徐々に適用拡大、AM装置増設を経て、昨年は月産100-200台生産機種の部品製造まで進めた経緯と、直面した課題に対し、主に形状設計やAM製造条件の工夫による対策により、従来ユニット部品数の大幅削減や組み立て、二次加工削減によるコストダウンだけでなく、性能向上も両立された具体例を紹介した。また当然必要な品質評価管理手法も開発し、今後もAM価値創出、設計と生産技術ノウハウを両輪で構築し、スマート生産の実現や他事業部へのAM製造の展開を目指すとのことであった。この事例は、AMを小さく始め、関係部署共同で徐々に正のスパイラルを回し、AM製造を自社の強みに引き上げている大変良い事例で、企業大小や製品種を問わず、共通して参考になる内容であった。
その他、日本AM協会×TCT Japan 共催セミナー「AMで新しいモノづくりのゴールドラッシュが来る」でも、経済産業省、及び複数企業からAMを実ビジネスに活用する提言や実例が紹介され、多くの聴講者が熱心に聞く姿が見られ、是非とも知って、聞いて終わりではなく、実際に取り組むことを始めるきっかけにしていただきたい講演であった。
国内外のAM学術研究の動向
TCT Japan カンファレンス 「先端研究開発事例」として、4つの大学の5名の研究者からの講演があり、医療分野におけるAMインプラントの国際標準や規格の動向、優位またはユニークな分野で、まだ無い規格を日本で出来れば世界的に優位に立てるという提言や、AMを核とした地域内循環システムの構築として、鎌倉市での産官学民参加型の資源循環社会創出プロジェクトの最新情報、また金属材料とAM技術、トポロジー最適化を含む数値解析技術の最新研究事例など、普段接する機会が少ない専門的な知識を得られた貴重な機会であった。加えて、一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会からは「いまさら聞けない3Dプリンターの基礎」や「3Dプリンティング海外動向報告 ~欧州にみる3Dプリンター最先端技術の紹介~」など幅広い情報提供もあり、どちらも満席で立ち見の方も大変多い講演であった。
まとめ
今回もTCT JAPANのセミナー主催展示会は、国内外から幅広い分野の講演者による講演が多数提供され、AMの全体像から、個別の目的や課題に対する答えまで、多くの方の参考になったであろう貴重な機会を提供された、主催者と講演者各位にはこの場を借りて感謝の意を表したい。またこの場では一部しかお伝え出来ないことをお詫びするとともに、得た情報を含め、引き続き様々な機会を通しお伝えしていきたい。
設計者からAMソフトウエア・装置販売ビジネスに20年以上携わった経験と人脈を基に、AMに関わるみなさんに役立つ情報とつながりをお届けしていきます。