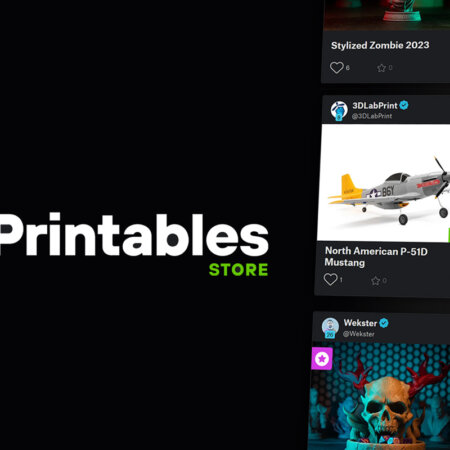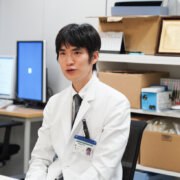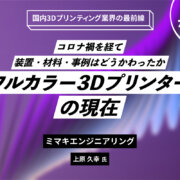富山の土で作られた万博トイレ、持続可能性を形に ― 浜田晶則氏の挑戦

2025年大阪・関西万博にて、魚津市出身の建築家・浜田 晶則 氏が設計・製作を手がけた新たな試みのトイレ施設が完成した。このトイレは、富山県産の土を用いた3Dプリンター製の外装パネルで構成され、終了後はすべて自然に還すという持続可能な思想のもとに作られている。建築設計事務所を率いる浜田 氏は、「この技術を将来的には被災地支援や海外展開にも活用したい」と語る。(上部画像は浜田晶則氏のインスタグラムより。出典:浜田 晶則 氏)
目次
自然と共生する空間演出。「Gorge(峡谷)」が描く土の建築美
本施設は「Gorge(峡谷)地層の狭(はざま)」と名付けられ、土の壁で人と自然とをつなぐ、峡谷を思わせる空間が表現されている。コンクリートを使った3Dプリント建築が広がりを見せる中で、土を素材とした事例は極めて稀であり、環境負荷の低減という観点からも注目されている。
環境への配慮と創意工夫
設計当初から、会期終了後に自然に還元することが前提であったため、セメントなどの定着材は一切使用されていない。強度を確保するためには、試行錯誤を重ねたという。わらや海藻由来の糊を加えることで粘性を高め、3Dプリンターの出力に適した土の配合が模索された。使用された土は、浜田氏の地元である富山県に加え、広島県、兵庫県・淡路島の3地域のものをブレンドしたものである。
魚津から万博へ。地層美をまとった土の建築が会場に登場
製作は東京と魚津にある浜田氏の拠点のうち、魚津の作業場にて行われた。3Dプリンターによって造形された土の外装パネル56枚と土ブロック45個は、自然の地層の風景を思わせるデザインで仕上げられた。表面には、地層が露出する峡谷の壁を模した起伏が施されており、自然と人工の融合が図られている。
これらの部材は、完成後に万博会場へ運ばれ、現地で組み立てられた。今回の万博では、20の休憩所・ギャラリー・トイレなどが公募により選ばれた若手建築家ら20組によって設計されており、浜田氏もその一員として参加している。
広がる応用可能性。サウナ小屋から災害復興まで見据えた挑戦
浜田氏の土を素材とする3Dプリント技術は、既に次なる活用先も決まっている。2025年10月には、奈良県でオープン予定のサウナ小屋の建築においても、この技術が導入される見込みである。
この取り組みは、建築の未来を示唆するだけでなく、地域資源の活用、環境負荷の最小化、さらには災害復興への応用可能性など、多くの可能性を秘めた実践的な試みといえる。
サステナビリティの関連記事
今回のニュースに関連するものとして、これまでShareLab NEWSが発表してきた記事の中から3つピックアップして紹介する。ぜひあわせてご覧いただきたい。