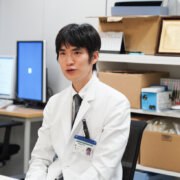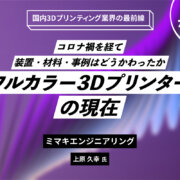惑わされてはいけない「事例の幻想」とは?

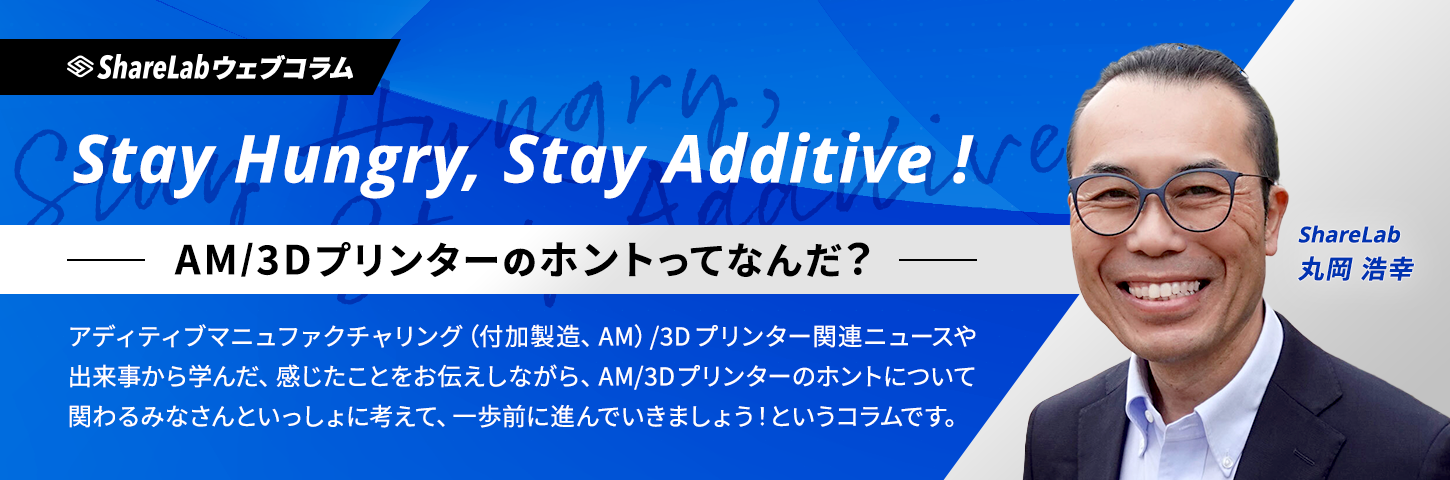
イントリックス株式会社 丸岡 浩幸 樹脂製品メーカーで設計を14年、その後AMソフトウェア・装置販売ビジネスに20年以上携わった経験と人脈を基に、ShareLabを通じてAMに関わるみなさんに役立つ情報とつながりをお届けしています。
「TCT Asia 2025 現地調査トピックス」ウェビナーを開催しました
桜前線がようやく北海道に達したとのことですが、同時に全国で7月並みの最高気温だったとのニュースもあり、私は寒いのが苦手なので、やっと寒さとは来冬までさよならできるかと安心しつつも、既に関西大阪万博会場での暑さ対策が話題になるなど、いったいこの夏はどうなるんだろうと心配しつつの今日この頃です。
さて、前回のコラムでお知らせしたとおり、中国上海で開催された展示会「TCT Asia 2025」のトピックスをお伝えする、ShareLabウェビナー「TCT Asia 2025 現地調査トピックス」を2025年4月15日に開催しました。100名を優に超える方にご参加いただき、誠にありがとうございました。大きな展示会でしたから、まずは中国AM産業の急成長の現状や、展示会の全体感と、金属、樹脂などの特徴的なブースや展示のトピックスだけを、できるだけ多くの方にお伝えできればと、参加無料で質疑応答を入れて1時間のウェビナーとしました。参加後アンケートにも多くの方にお答えいただき、概ね満足頂いたようですが、一方で「もの足りない」「樹脂の情報が少なかった」「もっと詳しい情報や事例が聞きたかった」などの声もいただきました。
実際のところ、日本の展示会と少し違ったのは、ブースでの製品やサンプルの言葉の説明は最小限しかなく、また聞いても言葉の壁や、こちらが商売の相手ではないこともあってか、あまり詳しく話してもらえなかったこともありますし、またサンプル自体も「大きさ」以外は、それほど新しい、または参考になる形状や用途事例のようなものは、ほぼ無かったのも実際のところです。思い返してみると、日本でも汎用化が進んでいる工作機械の展示会では、細かい新しさ、性能差や価格差をアピールするブースが多く、「画期的な活用事例」のようなものはほぼ見かけないことから、中国でのAMも既に「知らない、新しいもの」ではなくなり、展示会も自分たちの要望に合う、何をどこから買うかを探す、商談する場所になっているのかもしれません。また、特にAM製品や用途が広がっている今、見る人の立場や関心事によって、関心がある、参考になる視点や情報はかなり異なるので、万人に役立つ情報は限られており、よって展示会に行く方は、自分の目的と視点で情報を探すのは当然ですが、行かずに製品や事例の情報を得たい場合は、欲しい情報を絞った上で外部調査委託サービスを利用されることが、結局は有効な情報を得ることにつながると思います。
惑わされてはいけない「事例の幻想」とは?
上記のアンケートにも事例を知りたいという声がありましたが、私がAM産業に関わるようになってから今に至るまで、絶え間なくずっと聞こえてくる話として、AMの買い手からは「良い事例がない」「もっと具体的な成功事例が知りたい」「はっきり利益が数字でわかる事例がないと導入が難しい」、またAMの売り手からは「良い事例を多く出したいが、お客様からはなかなか出していただけない」「メーカーや海外の事例はたくさんあるが、日本のお客様には役に立たない」、というようなものでした。昔は事例が実際少なかったですが、いまは大量にあるのになぜこのような声が減らないのでしょうか?
もちろんAMに限らず、新しい技術や製品を売るにも買うにも「成功事例」や「ユーザーの声」が有効なことは否定しません。またAMの場合材料性能や形状精度に不安があるので、実際使われている事例があれば「使えるという安心や証明になる」という理由で事例を知りたいこともあるでしょう。ですが、これまで数多く見てきた国内外のAM活用事例や成功ビジネスの多くは、「先例がないもの」がほとんどだったと思いますし、実際に世界中で、他者の事例が導入や活用がヒントのひとつにはなれども、決め手になったり、そのまま模倣して成功した件がはたしてどのくらいあるのかと疑問に思っています。
これはAMがものづくり全体からすれば「出来ることが限られている」ことや、「極所、特別な需要や課題に対して有効」ということが背景にあるからかもしれません。一方で「誰にでも当てはまる公式回答例」や「似た仕事や会社で儲かっていて、同じことをすれば儲かる例」、「AMでしかできない画期的な用途例」というような事例があれば売れる、買えると探しているとすれば、それは幻想のようなものに惑わされているのに近いと個人的には思っています。逆に言えば、AMは先例がないものづくりやカイゼンに挑戦して先行者利益を得たり、これまで出来なかった製品やビジネス開発をまずとにかくやってみて、速く多く安く失敗することで先の可能性を見極める、または速く小さい成果にたどり着くのに使うのに適していますし、その結果の失敗や撤退の損害も比較的小さいとも言えます。つまり、事例の幻想を追うのに時間や工数をかける、または追って何もしないより、「先例が無くても、とにかく始めて試してみる」のが成功に共通している例ではないでしょうか?もしくは、事例は「近いけれども先例が無いことを探す」ことに使う方が良いかもしれません。
先日取材した展示会「INTERMOLD 2025」内で、テスラ社の電気自動車「モデルY」の分解調査特別展示がありました。

テスラ社モデルY 分解調査展示 (筆者撮影 一部加工)
話には聞いていましたが、これまでに見てきた乗用車と車体構造やモジュール、部品の材料や形状が違っていて、驚きました。これも先例がないものづくりの「事例」だと思いますが、こういう自動車が好例として世界に広がっていくとすると、日本の自動車製造産業も変わらざるを得ないと思いますし、自動車一存では生き残れなくなることも、ますます現実味が高まってきます。この展示はその警鐘でもあると同時に、新たな挑戦へのきっかけとしての狙いもあったのではと思いました。もちろんモデルYはひとつの事例で、これをどう見るかは見る人の視点で、毒にも薬にもなりますし、AMの活用事例もこれに似ていると思った展示でした。

ご存じの方も、既に購入して読まれた方もいると思いますが、おそらく世界のAMの全体像を最も広くカバーしている市場調査、分析、予測のレポートだと思います。また30周年版とのことで、ほぼAM産業の歴史と共に歩んできたことは素晴らしく、数値や予測が全て正しいとは思いませんが、内容は実情にかなり近いと思います。私も長年お世話になってきましたが、昔は海外の情報が少なく、まず最初に応用事例の章から読んで、「なるほどこの手があったか」と驚くことが多かったですが、歳のせいもあってか、正直そのような驚きは少なくなりました。それだけ他からの情報も増えましたし、AMが速く広くなりすぎて、さすがにこのレポートでも拾いきれないのかもしれません。それでも読まなければ知らなかった情報も多く、勉強になりました。

私は前職でこの件に関わるご縁を頂いていたので、受賞はうれしいニュースでした。一方、ニュースとしては受賞をお伝えするものですが、単にフルカラーMJTプリンターの活用事例というだけでなく、ボクセルデータとMJTプリンターの組み合わせが生む大きな可能性のヒントでもあります。私の勝手な見方ではありますが、ボクセルデータはAMしかできない価値を大きく広げる可能性があり、課題はデータのより簡単な作り方、共通ファイルフォーマットの普及、3Dプリンター側ソフトウェアのインポートと、プリントデータへの変換機能が出来ることで、これから世界各地で解決策や活用例が出てくることを期待しています。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!