2025年4月4日に日本科学未来館(東京)で「やわらか3D共創コンソーシアム」の7周年記念シンポジウムが、「やわらかスモールワールド~つながる、ひろがる、やわらかい未来~」というテーマで開催された。昨年の6周年記念シンポジウムに続き今回も参加したので、概要を報告する。(写真:会長挨拶をする やわらか3D共創コンソーシアム・会長 / 山形大学・教授 古川 英光 氏 記者撮影)
目次
「やわらか3D共創コンソーシアム」とは?
「やわらか3D共創コンソーシアム」は山形大学の古川教授を会長とし、「材料 “30年” を、材料 “3ヶ月” に」という目標を掲げ、アイデアづくりとそれを実際に形にするための “場” として、研究機関だけではなく世界の最新技術を持った企業や団体、山形県地元企業等も集まるプラットフォームとなることを目指している。
今回は前回よりさらに多くの、また多分野から講演者、参加者があり、会場の椅子を急遽追加するほど盛況であった。また今回は「3Dの枠を超えて、4D・食・国際展開・文化・標準化などを議論します」とのことで、冒頭の会長挨拶で古川教授は、様々な人によるつながりから課題解決ができる、そのつながりを「やわらかスモールワールド」と表し、今回のテーマとしたと述べた。
シンポジウムの詳細、プログラム、登壇者紹介は下記シンポジウムのウェブサイトを参照されたい。
https://softsmallworld.peatix.com/
基調講演①:草野 一俊 氏(信州大学 繊維学部 材料化学工学課程 木村研究室)
「私の履歴書」と題し、長年メーカーでCD-ROMドライブ製品開発に携わった経験から、「国内外問わず多くの人とつながる」ことが困難な課題の解決に重要であることを、実例を交えて話した。CDは最初は音楽用で、データ転送速度が遅かったが、磁気テープ、磁気ディスクに代わりマイクロソフトがCDでソフトウェアの提供を開始したことをきっかけにCD-ROMの需要が高まり、その後世界中で転送速度の倍々化競争が起こり、5年間で20倍速、その後32倍速となり、その後DVDに置き換わっていった。当時動きの遅い大メーカーより早く製品開発、発売をしたことで利益を得られたことや、そのためには価格が高くても優れた海外他社の部品をいち早く採用したり、競合メーカー間で技術を共用しあったエピソードなどを交え、現在の製造における課題解決にもつながる、含蓄に富む内容を話した。
基調講演②:中川 友紀子 氏(株式会社アールティ・代表取締役)
食品製造における人手不足の課題を、AIビジョンとロボットで解決を目指している同社の取り組みを紹介した。特に食品を扱う難しさとして、柔らかいものをつかむこと、形の決まっていないモノの認識と紛らわしさなどがあり、それらを解決すべく、AI画像認識システムを搭載する人型協働ロボット「Foodly(フードリー)」を自社開発、自社生産している。Foodlyは双腕人型ロボットで、ばら積みされた食材をひとつひとつ認識して取り出し、弁当箱などに盛り付ける作業を、ベルトコンベアラインで人と隣り合って安全に作業することが出来る。またロボット外装部品製造に3Dプリンティングを活用しているとのことであった。
会長講演:古川 英光 氏(やわらか3D共創コンソーシアム・会長 / 山形大学・教授)
昨年の活動報告として、山形大学と世紀株式会社で共同開発したフード3Dプリンターを20台販売出来たこと、2024年4月16~18日 スペイン ビルバオで開催されたFood 4 Future展示会に出展したことを報告した。また今後の活動として、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)シグネチャーパビリオン「EARTH MART」(テーマ事業プロデューサー:小山薫堂)にて、あらゆる食材を凍結粉砕してパウダー化することで食の新たな可能性を広げる展示を行うことを発表した。
部会活動報告
<食品部会>
- 日本科学未来館のオープンラボでフードプリンターによる企業共同開発。2024年12月に試食会を開催し、100人を超える来場者
- 空想宇宙食学会を発足 メタバース上で「月の駅」建設中。宇宙ステーション向けフードプリンター開発へ
- 「4Dグミリーグ」発足、独創的なグミ作品による競技。「実際に食べられる」「食べられないが動く、変化する」「仮想」などの部門で作品募集予定
<医療部会>
- 「メディカルクリエーションふくしま」に出展。医療関係者との出会いの場を作ることに重点
- 医療機器メーカー 富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング企業見学実施
<ゲル部会>
- 採択されている「NEDO先導研究プログラム/マテリアル・バイオ革新技術先導研究プログラム」において 500万円で買える4Dプリンター、異種軟質材料積層「キメラ4Dプリンター」開発
- 「4D Printing Summit」を今年1月に開催。次回7月開催予定
<モビリティ(構造)部会>
- 昨年6月に3Dプリンターメーカー エス・ラボ社見学
- 柔らかい材料と3Dプリンタならではの内部構造を掛け合わせて生まれる機能によるモビリティアイテムの検討、今年度、モビリティアイテムの具体化へ
- 「未労」をコンセプトに、移動により体に受ける負荷を体幹を鍛える力に変えるような製品開発も
- モビリティ(ウエルネス)部会に部会名を変更し、看護理工学や医療部会と連携
<ソフトマシン部会>
- ソフトマシン(アート)部会に部会名を変更
- 多摩美術大学 CMTEL素材研究室や3DプリントラボStudio fabCAVE 見学
- 小川准教授が山形大学に研究室新設 ふわっとしたイラストやアイデアからモノをつくることは大事
パネルディスカッション 「第1部 4Dが拓く未来」
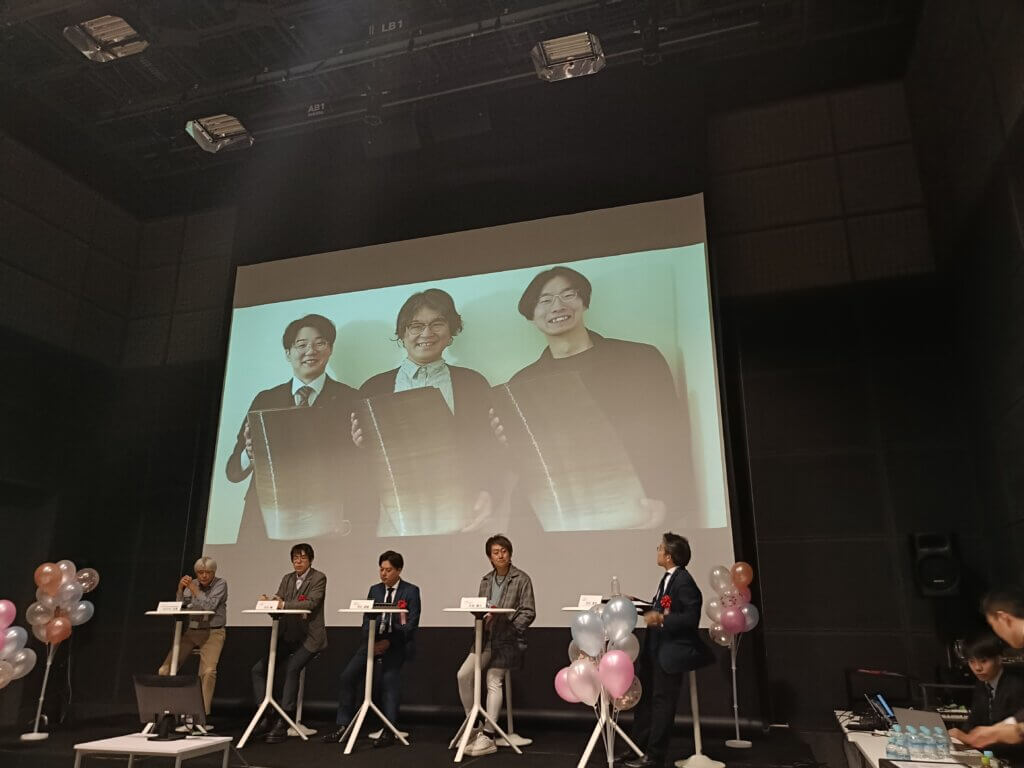
パネラーからの主な発言:
田中 浩也 氏(慶応義塾大学環境情報学部・教授/SFC研究所ソーシャルファブリケーションラボ・代表)録画参加
大阪・関西万博日本館「双鶴(そうかく)共創プロジェクト」は循環がテーマで、藻類とバイオプラスチックから3Dプリンターで、会場で使うスツール60脚を製造。2台のアームロボットプリンターを含む、造られる過程を見せたい夢がかなった。「やわらかいものづくり」は日本の伝統につながる。
谷山 詩温 氏(大阪公立大学 スーパーシティ研究センター・客員研究員/四国大学 学際融合研究所 次世代ICT教育開発研究会・特別研究員/株式会社AVAD・代表取締役)
「4Dグミリーグ」は突き抜けるパワーで爆発的に活躍する人を応援したい。情熱は出会う人によって変わる。
小川 純 氏(山形大学 大学院理工学研究科情報・エレクトロニクス専攻・准教授)
4Dはまだブレインストーミングできる領域。見ていると変化する面白さをもつ「崩壊」をテーマに研究したい。
吉水 康人 氏(キオクシア株式会社)
東京オリンピックが日本食を広めたように、大阪万博を起点に4Dプリンティングが世界に広がる機会。
講評 モデレータ:佐々木 直哉 氏(山形大学・客員教授 / 立命館大学・客員教授)
コンソーシアムでは7年間でフードプリンターができ、試食会もできるようになった。目標ありきではなく、「ブリコラージュ」の状態であるとともに、社会実装への難しさ、課題も見つけていく必要がある。
パネルディスカッション 「第2部 未来の食文化」
モデレータ:吉本 陽子 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)
食べ物は変わらないけれど、作り方は劇的に変化している。カスタマージャーニーから考えることが重要。消費者はどう作るかより「あっ」と思うか。ビジネスを考えると行動変容が必要になる。人は欲しいものに気づかない。価値形成には選択肢が多い方が良いので選択肢を繋げる接点が必要。
中川 友紀子 氏(株式会社アールティ)
食はエモーショナル。ロボットが文化的にも融合できればよい。
田中 宏隆 氏(株式会社UnlocX・代表取締役CEO/ SKS JAPAN・Founder)
フードテックは過去を知って未来を知ること。我々は何を食べてきたのか。食文化を守る、残すには進化しながら テクノロジーでアップデートする。
赤星 良一 氏(RDBコンサルティング・代表/食品技術士センター・副会長、技術士[農業部門農芸化学])
食文化は簡単に変わらないと思っていたが、これまでの講演を聞くとそうでもないと思えた。地域の食文化に影響するのは「その地で食べられるもの」「体質」「宗教」。インドでは牛肉を食べないため多くが慢性的に貧血。北欧では食を楽しんでいない。そのようなことを(フードプリンティングが)解決できるか。
まとめ
昨年のシンポジウムと比較して、初めて参加された方、また半導体製造、ロボティクス、建設、省庁などより広い分野の方も増え、共創の広がりを実感した。また今回特に「フードテック」「4Dプリンティング(作られたものが時間または何かの入力で形状や色が変化する)」に関する話題が増え、特にフード3Dプリンティングはスペインとの連携や、国内でも社会実装や新たなビジネス創出へ動き出す企業間など、共創の機運が高まっている変化が見られた。一方、工業用途AMにも共通する、より良い活用に必要な「需要創出と社会実装・ビジネスモデルの設計」「材料開発と形状設計方法」「規格整備と品質管理」はフードプリンティングにも共通する課題であると感じた。その解決には本シンポジウムのテーマであった「つながりとひろがり」が重要であることに、あらためて気づくことが出来た良い機会であった。また大阪・関西万博が海外発信を含め、様々な3Dプリンティングの認知や新たな活用の起点となり、やわらか3D共創コンソーシアムの活動もより発展、具体化していくことに期待して、今後も注目していきたい。

丸岡 浩幸
設計者からAMソフトウエア・装置販売ビジネスに20年以上携わった経験と人脈を基に、AMに関わるみなさんに役立つ情報とつながりをお届けしていきます。






