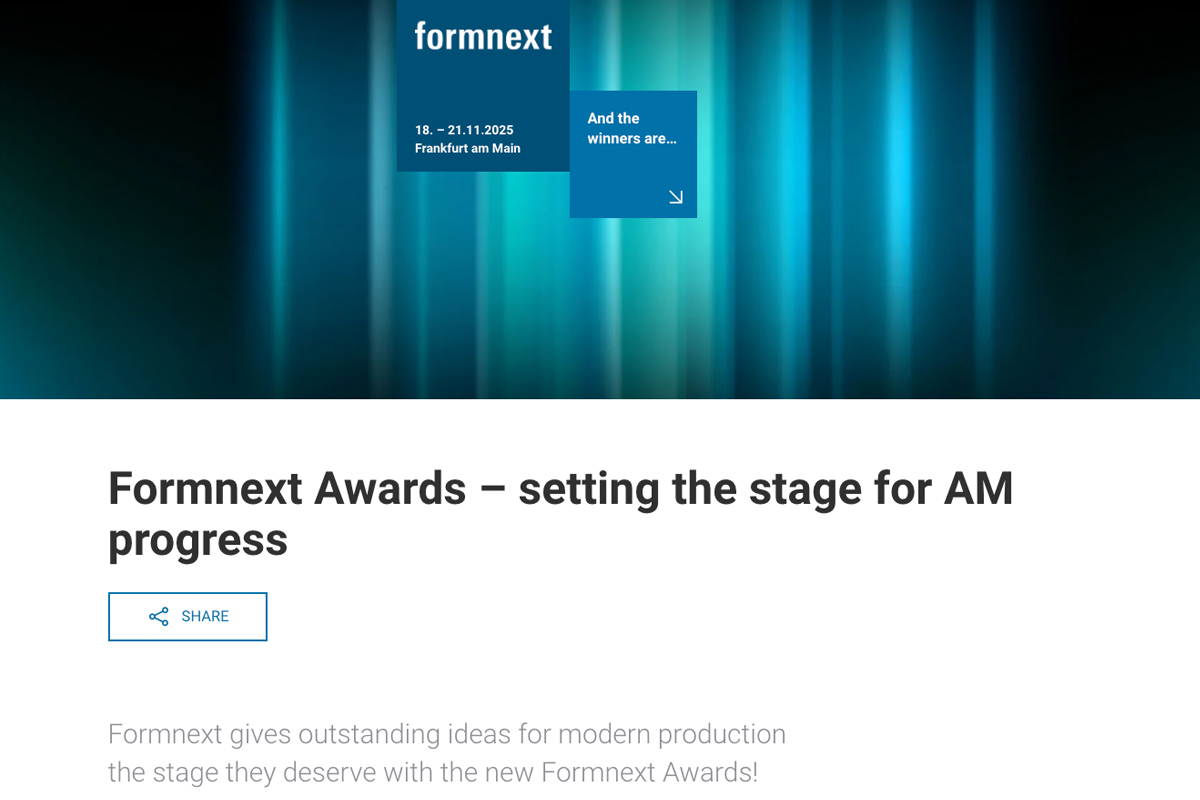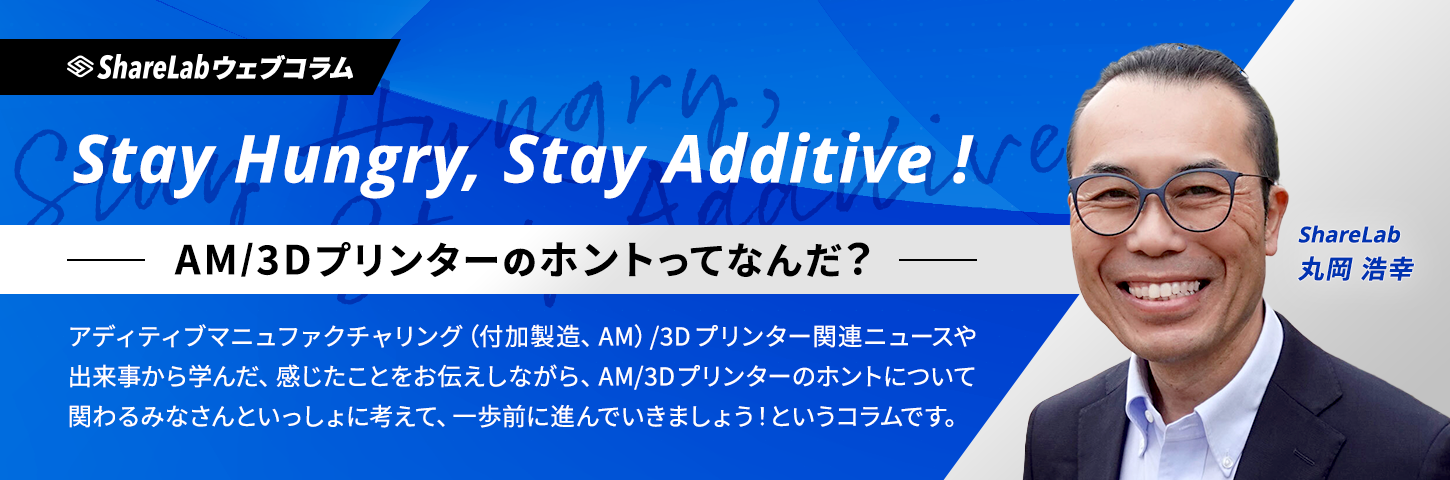
今回はベルギーで書いています
東京周辺の5月は、日中過ごしやすい陽気の日が多いはずですが、今年も含め近年は寒いか暑いかの日が多く、ちょうどいい日が少なく、いよいよ日本も「四季のある国」から「二季の国」に変わってしまうのでしょうか?残念な一方、こうなる一因は自分も含めた現代人の生活にあることを思えば、文句も言えない気もします。そのような中、このコラムは出張中のベルギーで書いています。こちらは昨日は日中暑く、今日は半袖だと涼しい感じですが、からっとしていて、ちょうどいい感じです。こちらの人に聞くと「天気の悪い日が多い季節」とのことですが、たまたま運がよかったと思い、ありがたく「ちょうどよい」を楽しんでいます。
AMはもっと「必要」から遡るべき!
ベルギーに来ているのは、ある調査依頼案件のため、読者にもご存じの方が多いマテリアライズ社ベルギー本社訪問のためです。私は約20数年前から10年弱の間、マテリアライズ日本法人(現マテリアライズジャパン株式会社)に勤めていて、その間に何度も来ていましたので、今回は久しぶりの再訪でした。

写真手前のビルは当時と変わらないのですが、奥に大きな社屋が増えていて、同社の成長を実感しました。以前ShareLabでインタビュー記事でお伝えしたこともある、創業者のヴァンクラン会長ともお会いでき、他にも久しぶりの方々と話すことが出来ました。
同社のソフトウェア製品を使われている方も多いと思いますが、2024年に総計210万個をAMで製造販売する同社の、世界中の様々な用途を知る方々と話す中で、AMを「必要」から遡って考える大事さにあらためて気づいたことがありました。それも含め今回訪問の詳しくは、いずれ別の機会でお伝えしたいと思っていますが、偶然日本で似た話があったことを思い出しました。
こちらも以前このコラムでお伝えした、山一ハガネ社のホームページの下記のレポートを紹介したいと思います。
3Dプリンタ発祥の地・名古屋から未来へ。「縁」がつむぐ技術の系譜-3Dプリンタ発明者小玉秀男氏来社レポート-
AMに携わる多くの方もご存じの小玉秀男氏が、発明の経緯やその後について話されており、その中で、「自分が困っていたからこそ、『こういうものが必要なんだ』と自然に思えた」という話を含め、AM関係者だけでなく、ものづくりに携わる多くの方にも参考になる内容が含まれていました。
自省も含め、AMの売り手も買い手も、往々にしてAMそのものや、AMの現状のQCDや性能から話を始めたり、用途を考えたりしがちですが、AMの外の方々は、「必要」から遡ってAMにたどり着いたり、評価をされることも多くあり、そういった方々は、必要が満たされるのであれば、AMかどうかはどちらでもよい場合があります。まずはAMの外と中の人が「必要」や「目指すこと」を共有し、更に協働していくことが増えると、これからAMも新たなステージに進む可能性が増えると思います。
いつもながら、時差ぼけが治らないうちに帰国することになりそうですが、今回の話題についても帰国後多くの方々と話していきたいと思っています。
工場長サミット in Aichi パネルディスカッションに登壇します
下記の通り開催予定のパネルディスカッションにパネリストとして登壇予定です。講演後ネットワーキングのセッションもありますので、展示会と合わせぜひご参加ください。
開催日時:2025年6月5日(木) 13:30~14:15
タイトル: 工場長サミット in Aichi
主催: モノづくり日本会議
会場: 展示会 AXIA EXPO内 メインステージ (定員300名)
テーマ:「進化する『AM』技術、先進活用企業にみるモノ・コトづくり変革」
登壇者:
株式会社アイシン グループ生産技術本部 試作部実証試作室先進開発実証グループAM技術主幹 山本 英司 氏
株式会社日本精機 常務取締役 松原 雅人 氏
イントリックス株式会社 ShareLab事業部 事業開発ディレクター 丸岡 浩幸
モデレーター:イントリックス株式会社 社長 氣賀 崇
イベント詳細 https://newswitch.jp/p/45601
聴講申し込みはこちらからお願いします。
ShareLabニュースにもう一言
建設業界も労働力不足やサステナビリティ対応など、待ったなしの「必要」があり、その解決にAMを活用する例が多く見られます。この記事もそうですが、それより驚いたのは、Starbucksは「落ち着いて座って時間を過ごす」店だと思い込んでいましたが、アメリカではドライブスルーや立ったままというニーズに応える店舗が「必要」になったことでした。
熱交換器にAMが使われる例も「必要」から遡るケースが多いように思います。またこの記事からは、熱交換器の「必要」を満たすだけでなく、「自動車」というシステム全体の必要をAM製熱交換器が満たしていること、また自動車開発企業と熱交換器企業が早い設計段階から協働していることは、自動車関連以外の方々にも参考になる例ではないかと思います。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!