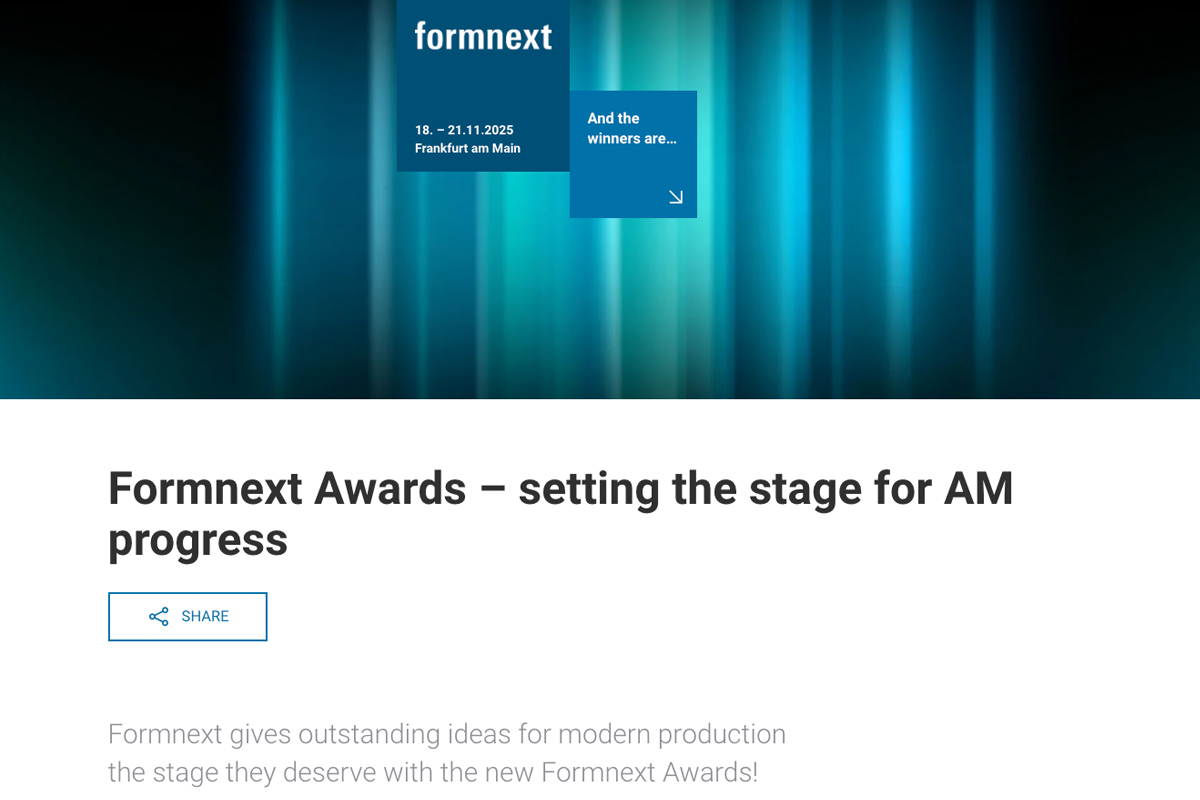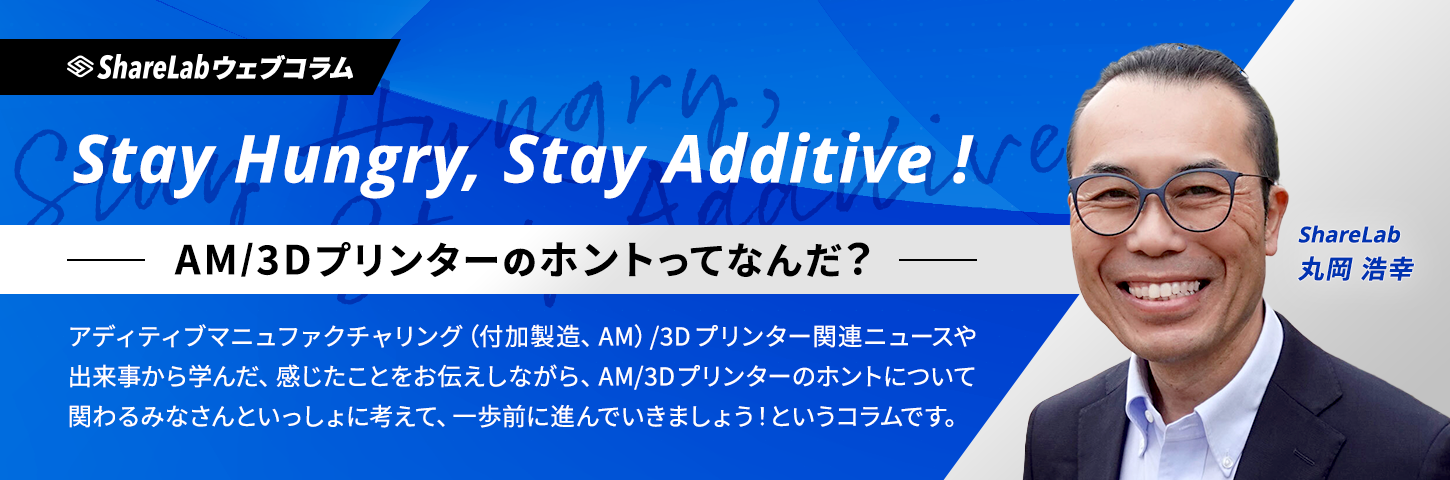
AMがアツいシューズ産業
8月に入るや否や、全国的に記録破りの酷暑になっています。私は住む地域の夏祭りを数年前から手伝っていて、ここ数年は雨が降ることより「暑さ」が心配の種でした。でも今年は更に季節外れの台風接近があり、開催直前まで風雨が強くやきもきしましたが、何とか開催、片付けも暑かったですが無事に終えることができ、とても良いお祭りになりました。お祭りの内容も、暑さや参加する人の求めることの変化でだいぶ変わりましたが、最近のシューズ産業もいくつかの要因が重なって、AM活用が急にアツくなっているようです。
やっと買えたAM製パーソナルフィッティングシューズ
歴史を振り返ってみると、3Dプリンターが世に出てきた30年近く前から、次のような利点や価値がある、またはこれから実現すると言われてきたと思います。
- これまでの作り方では出来ないデザインや形状、性能(例えば軽量や部分的に硬さが違う一体品など含む)が作れる
- 使う人それぞれにぴったり合った形状が出来る
- 少量なら型を作ったり、削ったり、組み立てたりするより速くできる
- 作るときに捨てる材料が少ない など
私自身もAMを知ったときに、「人それぞれのメガネや靴ができる!」と誰でも思いつくことを思った記憶があります。ところが、間もなく補聴器の耳栓や、疾病治療や予防目的の靴の中敷きなどは、パーソナルフィットの製品が海外で出てきましたが、それ以来10年、20年経ってもなかなか自分の生活レベルで買える製品が世の中に出てきませんでした。
特にシューズにおいて上の4つのAMの利点は、作る側にも使う側にも価値が高そうなのですが、3Dプリンターと材料のQCD性能や、計測、設計、製造、検査、品質管理のツールと現状性能を知れば知るほど、「これはしばらく実現しそうにない」と少し前まで思っていました。その後、海外スポーツシューズメーカーがソールクッションだけ、また斬新なデザインのAM製造シューズを発売し始めたものの、ネットだけ、数量限定、高価、しかもパーソナルフィットではない商品で、あまり買う気になれませんでした。
ちょっとあきらめかけていた昨年末に、ミズノが世界で初めてAMソールによるパーソナルフィッティングシューズ「3D U-Fit」の発売をShareLabでもニュースでお伝えしました。個人的には「ようやく、それも日本の会社が出してくれた!」とうれしかったことや、いくつかの偶然もあって、自分にとっては高額でしたが、思い切って発売早々買うことにしました。
右は受け取った直後に自撮りした写真です。第1印象は、圧力が足底均一で、ホールド感も良く、これがパーソナルフィッティングの効果かと思う反面、つま先はちょっと緩い、濡れた路面は滑りやすい、脱ぎ履きしにくい(今は慣れた)、でした。

その後上海での展示会、欧州出張、国内の展示会やイベント、大阪・関西万博取材にも履いて行ったので、今のところおそらく最も長距離を移動したユーザーかなと思っています。これまでの靴では、長距離を歩くと痛み、疲れが出やすかったのですが、クッションも硬すぎず柔らかすぎず、疲れが少なかったと感じています(高額出費肯定バイアスはかかっているかもですが)。余談ですが、仕事で履いている間に、この靴がAM製だと気づいた方はこれまでひとりもいませんでした(業界関係者で私のメガネがAM製と気づいた方は数名いましたが…笑 それだけフツーの靴ということです)。
その後また不思議なご縁があり、3D U-Fitの開発をされた方にインタビューも出来て、開発者の想いや苦労、より深く製品や性能を知ることが出来て、私が感じた効果が開発者の狙いと合っていたこともわかりました。
シューズ産業にみる AMが広がるパターン
3D U-Fit以外に、昨年から最近にかけて、次々とAM製シューズが世界各地で発売されたように思います。特にアッパーソール一体成形、メッシュタイプが増えました。最近驚いたのは、スイスのメーカー「On」が発売した「LightSpray™」で、アッパーのみ、パーソナルフィッティングではないですが、上記のAMの利点ほぼ全てが当てはまっていると思います。
そこで、なぜ最近急にシューズ産業にAMが広がったかを考えてみると、以下の要因が複合的に、同時期に重なったのではないかと思います。
・AM工法と材料の進化
PBF、VPP、MEXそれぞれの工法で、シューズに合う柔軟性、弾力性、耐久性、耐環境性(紫外線、水、皮膚接触含め)、多色の材料が急速に開発市販され、かつ価格も下がり、外観品質も生産能力(多数台並列含め)もある程度のレベルになってきたことは大きな要因だと思います。
・計測と設計のツール、コスパ進化、省人化
ミズノのインタビューでもわかる通り、足形デジタルスキャナーと3Dデータ化ソフトウエアの汎用市販品が無かったら、仮に上記のAMの進化が起きても開発、商品化は難しかったと思われます。加えて、複雑曲面を含む靴形状の設計でも、メーカーノウハウを反映し、3Dデジタル設計とAM造形設計が出来るソフトウエアがあることは、必要条件だと思います。
・産業を取り巻く環境の変化
一般の大量生産市販シューズは、一般にアッパーは多種の布地やシートに印刷、裁断による多数の部品を作り、ソールも素材ごとに金型で成形された多数の部品を全サイズごとに作り、多くの手作業による縫製や接着などで組み立てられ、捨てる端材も多く、また売れ残り廃棄も含め、資源消費や環境労働負荷が高いとされています。それに対する社会や消費者からの対策の圧力が急に高まったこともAMが広がる大きな後押しになったと見ています。
・革新する人材の増加
上記3つの条件がそろっても、やはり最後はシューズビジネス、デザイン、製造を革新したい人がAMに突破口を見出し、前回のコラムに書いたAM活用に成功する条件の人材が増え、実現に向けて動いたことは最も大きな要因だと思います。ミズノの北氏も正にそのような方でした。
上記4つの要因は、シューズ以外の産業や用途でも、AMが広がる要因として共通していると思いますし、4つが並行して進化することが必要だと思います。逆にうまくいかない場合は、4つのどれが欠けているか、それをどう補うかがカギになるのではないでしょうか?
ShareLabニュースにもう一言
建築土木産業もシューズよりAMがアツくなって、広がっているようです。大阪・関西万博でも多く使われていました。このニュースは海外のAM関連メディアも報じていて、むしろ日本よりも高い関心が寄せられているようで、「日本すごい!」というコメントも見ました。建築土木産業でも上記の4つのAMが広がる要因が当てはまると思います。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!