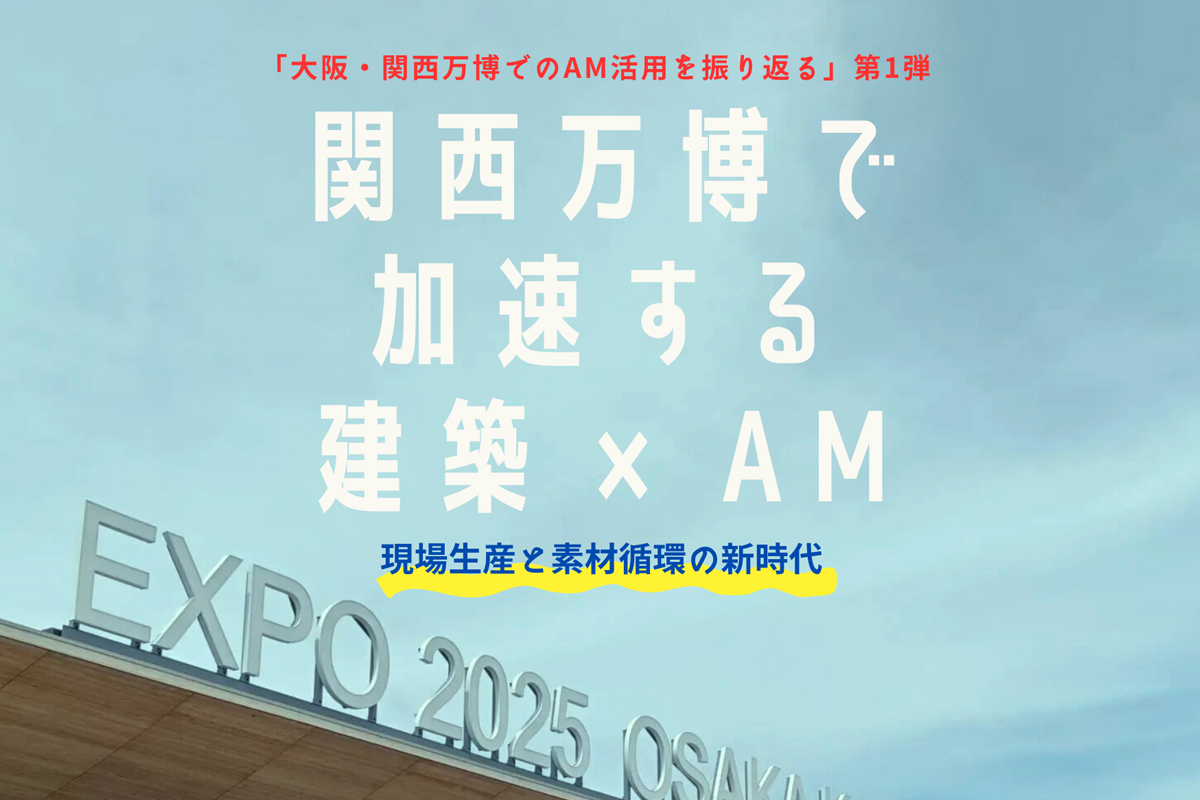2025年10月、半年にわたって開催された大阪・関西万博が閉幕した。
「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げたこの万博は、AIやロボティクスと並び、3Dプリンティング(Additive Manufacturing=AM)の社会実装を体現する舞台となり、とりわけ建設・都市インフラ分野では、AMを活用した構造物や素材循環の実験が進み、建築そのものがデジタルファブリケーションによって変わり始めた。
今回は、シェアラボニュース連載「関西万博でのAM活用を振り返る」(全3回)の第1回として、当時シェアラボニュースで紹介した記事をもとに、万博関連の建築・都市AM活用を振り返り、閉幕を経て見えてきた“建設の未来像”を探ってみようと思う。
目次
再生樹脂で挑む!竹中工務店×CAFBLOの森になる建築
竹中工務店とダイセルは、大阪・関西万博「大地の広場」で、生分解性樹脂「CAFBLO(カフブロ)」を用いた大型3Dプリント建築「森になる建築」を共同開発した。天然由来樹脂を国産プリンタで造形し、2024年には「世界最大の生分解性3Dプリント建築」としてギネス認定。展示後には素材を粉砕・再利用する計画も進められ、設計から再資源化までを循環させる新たな建築モデルを提示した。
URBAN RESEARCHが示した“未来のストア体験”
URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)は「セービングゾーン」に未来志向の店舗空間を出展。3Dプリント什器や再生素材家具を用い、ファッションとテクノロジーを融合した新しいライフスタイル提案を行った。AMによる柔軟な設計・製造を通じて、地域と人をつなぐ“循環型ブランド”への進化を体現した。
詳しくは、アーバンリサーチの特設サイト「URBAN RESEARCH EXPO2025 STORE(公式)」を参照されたい。
3Dプリントが生んだ!VOID×Pond Edge Farmの島の蜃気楼
建築デザイン・空間演出のVOIDとPond Edge Farmは、再利用可能な樹脂素材と大型プリンタを使い、トイレ施設「島の蜃気楼」を設計・製作。光や風景を反射・透過する3Dプリントパネルが環境と呼応し、建築が“風景の一部”として存在することを示した。解体後の再利用も前提にした設計で、循環型建築の新たな表現となった。
建築を“細胞”で形づくる!ExtraBoldの挑戦
ExtraBoldは「いのちめぐる冒険」パビリオンで、是永商会と協力し、海水コンクリート用の3Dプリント型枠を製作。大型プリンタ「EXF-12」により生命的なテクスチャーを造形し、短期間で量産化を実現した。再利用や素材リサイクルにも配慮し、デジタル建築を“循環するものづくり”へ拡張した事例である。
閉幕後に残された“新しい建設文化”
大阪・関西万博は閉幕したが、そこで実証されたプロジェクト群は、日本の建設文化が新たな段階へ進み始めた確かな兆しを残した。
現場で造り、分解して再利用し、地域で支える。AM技術はその核となり、設計から素材循環までをデータで結ぶ新しい建築モデルを提示した。
金属から樹脂、バイオマス、リサイクル材へと広がる素材の多様化は、建築を“循環するプロセス”へと変え、試作技術が社会を形づくる基盤へと進化した今、建築の未来は「造る」から「つなぐ」へと向かっている。
次回(第2回)では、医療・食など、“いのちとくらし”の分野でAMがどのように人間中心の価値を生み出したかを振り返る。