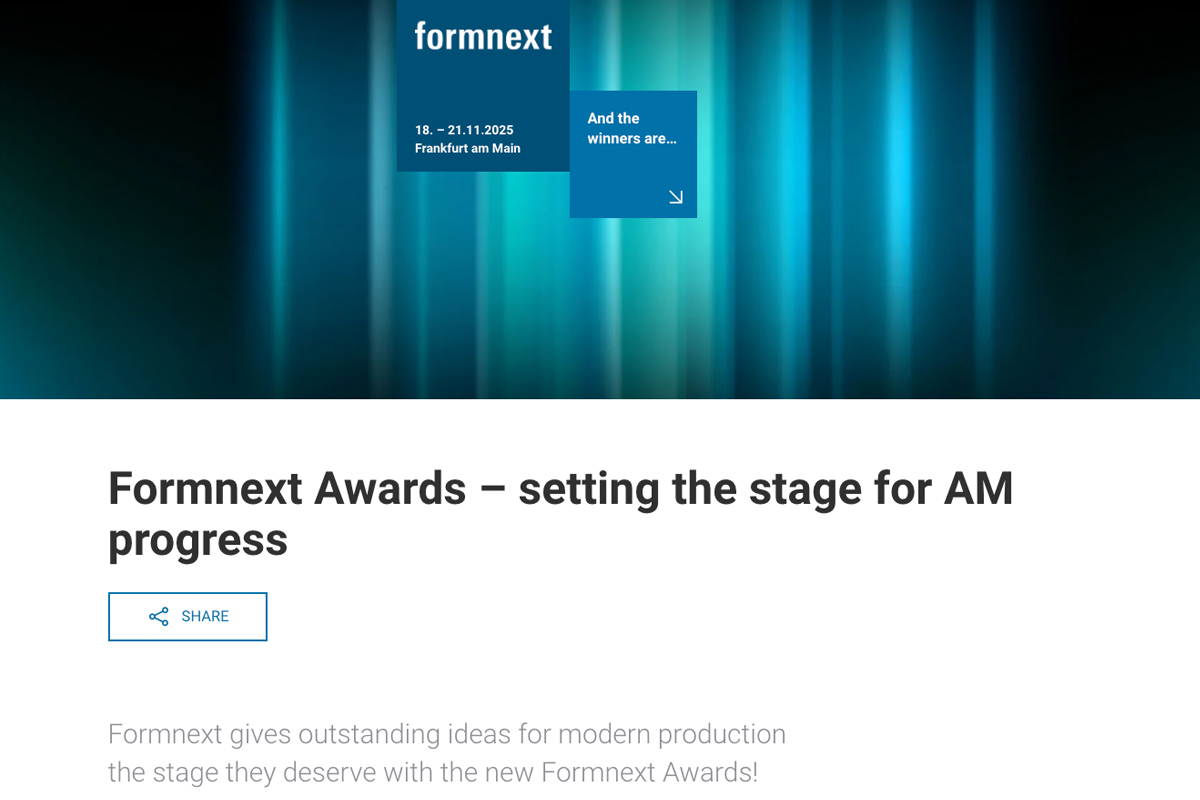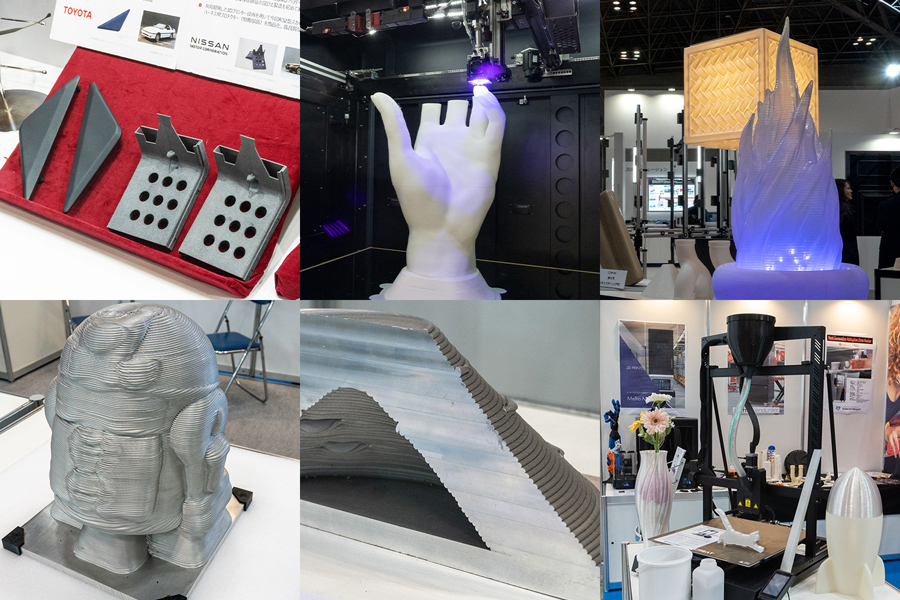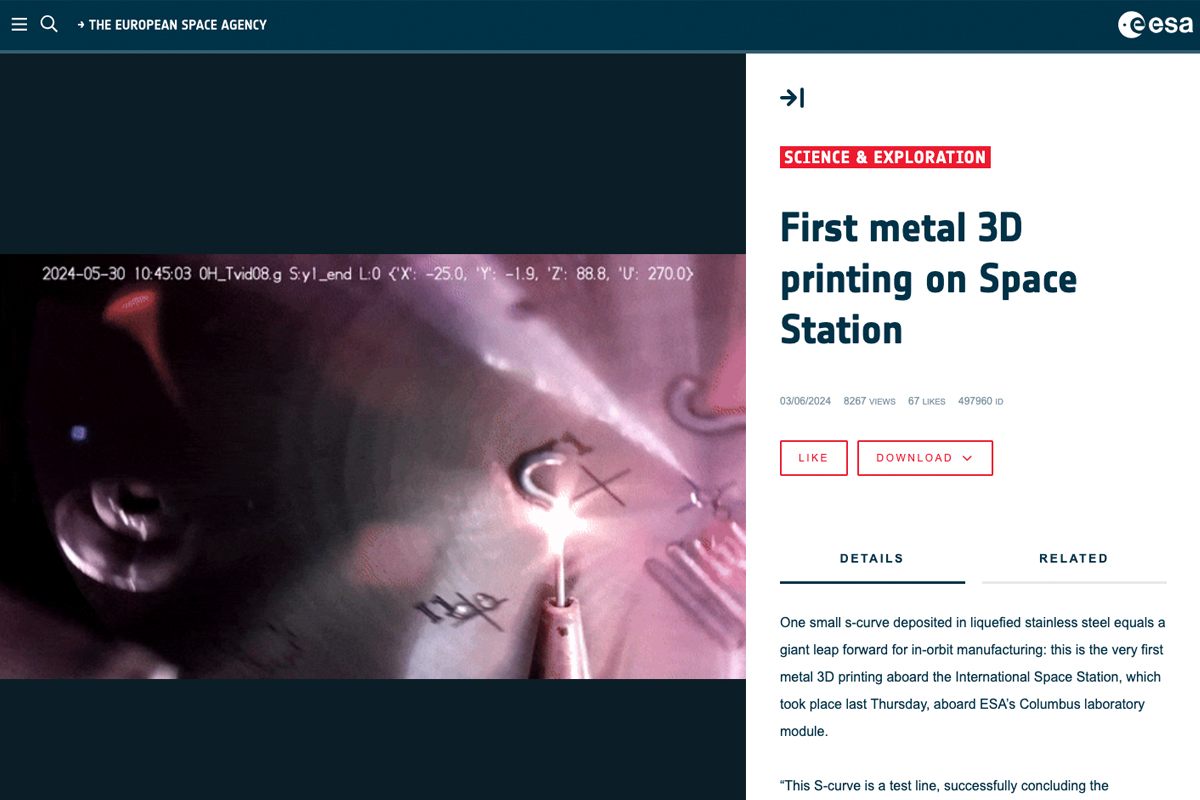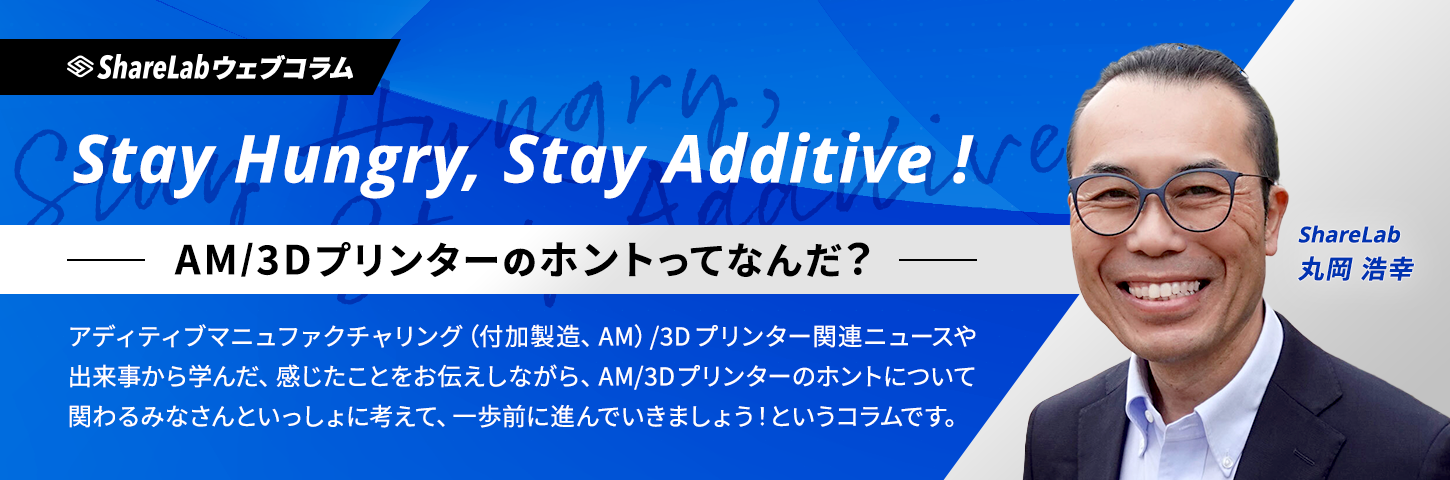
暑中お見舞い申し上げます
7月初めの前回のコラムから少し間が空いてしまいましたが、結局その間に戻り梅雨もなく、長い夏に突入してしまいました。天気予報を見ていると、沖縄の那覇の最高気温が30℃を下回っている日があり、「沖縄に避暑に行く」という時代になるのかもしれません。3Dプリンターを使う場所は冷暖房で温湿度が調整されている部屋が多いですが、工場で2次加工をしたり、ShareLabニュースでも「大阪・関西万博 現地取材レポート」でお伝えしたような建築土木用3Dプリンターを使う方は、暑い場所での作業もあるでしょう。みなさんの体調管理はもちろん、3Dプリンターや材料の温湿度管理にも気を付けて夏を乗り切りましょう。さて、最近各地のいろいろなイベントに行く機会が多くあり、そこでAMの活用に成功している方々のお話を伺うと、いくつかの共通点があることに気づきました。今回はその話題です。
AMの活用に成功する人の共通点
ここ数か月の間に、パネルディスカッションの司会や登壇、ShareLabTVのインタビューや対談動画収録など、AMを使う多くの方々から直接お話を伺う機会をいただき、ありがたいご縁に感謝をしています。それを通して感じたのは、AMの活用に既に成功されている、または目指されている方々には以下のような共通点があるようです。
過去に苦労して、AMに解決の希望を見出す
AMと出会うパターンは、突然経営層から研究・活用するよう指示されたり、何に使えるかわからないけれども新しいから使ってみたり、新しいビジネス開発に良い工法を探した結果だったり、本当にいろいろあります。ただし、どのパターンにおいても、初めは会社や周りの関心や理解もあっても、より高い要求の用途に使おうとしたり、実用品製造に使おうとしたり、投資回収や収益を求められるようになってくると、急に反対勢力が出てきたり、周囲からの風当たりが強くなったり、人が離れて行ったりという「逆境」に見舞われることも多いです。しかし、過去に設計や製造においていろいろな苦労をしたり、技術や環境の壁によって断念したり、これから先の変化に懸念を覚えた後に、AMがその解決策になるかもと気づいた、または信じた方々は、使ってみてAMの足りない点、悪い点があっても、「過去の苦労や壁に比べれば、もしくはそれが解決できるなら」という見方ができ、その結果AMを好意的に見続けられることで、逆境や課題を乗り越えて成功までたどり着けた共通点があると思います。中には「AMは難しいと言われているからこそ燃えた」という「逆境歓迎」的な方もおられましたが、変化を良しとし、かつAMだけにこだわらず、現実的な最適解を求めることに前向きな点も共通していると思います。
独りぼっちにならない
実はこれが一番大事な共通点ではないかと思っていますが、どうしても逆境に追い込まれると、味方がいなくなる、自分だけで解決しようとしてしまうということが起こりがちです。そこで、成功している方々に共通しているのは、とにかく外に出かけて情報を集めたり、他業種であってもAMに関わる人と人脈を作ったり(SNSをうまく使う方も増えている)、早くから専門家に頼ったりしていることです。また、例えば社内ではAMの品質、性能、価格について、これまでの社内常識から否定的に見られても、社外の関係者や買う立場の方に聞いてみると、好意的な反応が得られて、それを社内に持ち帰ると急に風向きが良くなったりする場合もあるようです。言い換えると「外の力をうまく使える」方々とも言えるでしょう。
粘り強い
AMは逆風に吹かれる場合と、「それが出来たなら、もっと高度に、広く使おう」という、AM独特の魔力のような追い風に吹かれる場合が多く、どちらにしても乗り越えるのに苦労や時間を要したり、乗り越えたらまた次の山という繰り返しになることも多いのですが、どちらにしても結局は粘り強く取り組み、挫折寸前を乗り越えた後に、成功軌道にたどり着いた方が多いと思います。その軌道がわかると、別の活用法も見え、さらに広がることもあります。その原動力は、上記3つの点が相互作用として生まれていることも共通していると思います。
上の3つの点は日本に限らず、私が知る限り世界のどの地域にも共通しているだけでなく、AMの供給側(装置販売、サービス販売など)で成功している方々にも共通していると思います。
言うまでもなく、AMは装置、材料、デジタルの技術が活用成功の欠かせない要因ですが、結局最後に使う「ひと」の要因は、それら以上に大きく、大事だと思っています。みなさんはいかがでしょうか?
参考情報
今回の話題の参考として紹介します。モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が今年6月5日に「工場長サミット in Aichi」を開催し、その中で弊社代表取締役 氣賀と丸岡が企画登壇協力した、金属AMを導入活用をしている方々とのトークセッションがあり、その記事が下記サイトで公開されています。記事ダウンロードもできます。ぜひ読んでみてください。
https://www.cho-monodzukuri.jp/u/jdo7o4b5sp/gdacntjcp7vcdu

また、私が関わっている案件の中で知った下記を紹介します。AMを医療機器や部品に活用しようとされる方々の課題解決に、役立つ知識や情報が詰まった書籍です。
「医療機器の力学的安全性評価の基礎知識 -医用材料・高適合化・積層造形技術-」
著者:岡崎義光 出版:薬事日報社
薬事日報社オンラインショップ
https://yakuji-shop.jp/smp/item/9784840816557.html
ShareLabニュースにもう一言
このセミナーでも講演やパネルディスカッションから、上記の共通点を多く感じました。ひと昔前と比べると、企業の大小を問わず、AMの導入や活用の実際の苦労や体験、乗り越え方を広く正直に話してくださる方が、国内でも本当に増えてきて、とても良いことだと思います。またこのように「まず話す」ことは準備が大変だったり、緊張したり、苦労を伴いますが、ほとんどの場合、結果として苦労を上回る情報や人脈が得られることも、これまで多く見てきています。ぜひ「まず話す」ことから始めることをお勧めします。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!