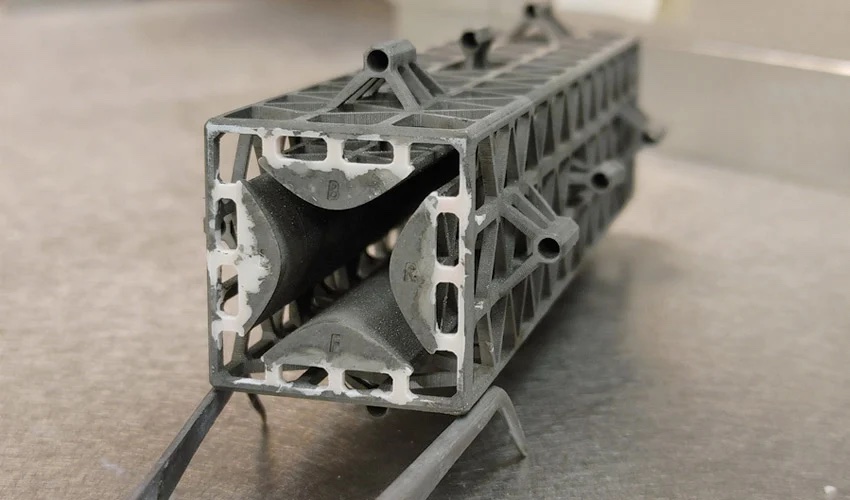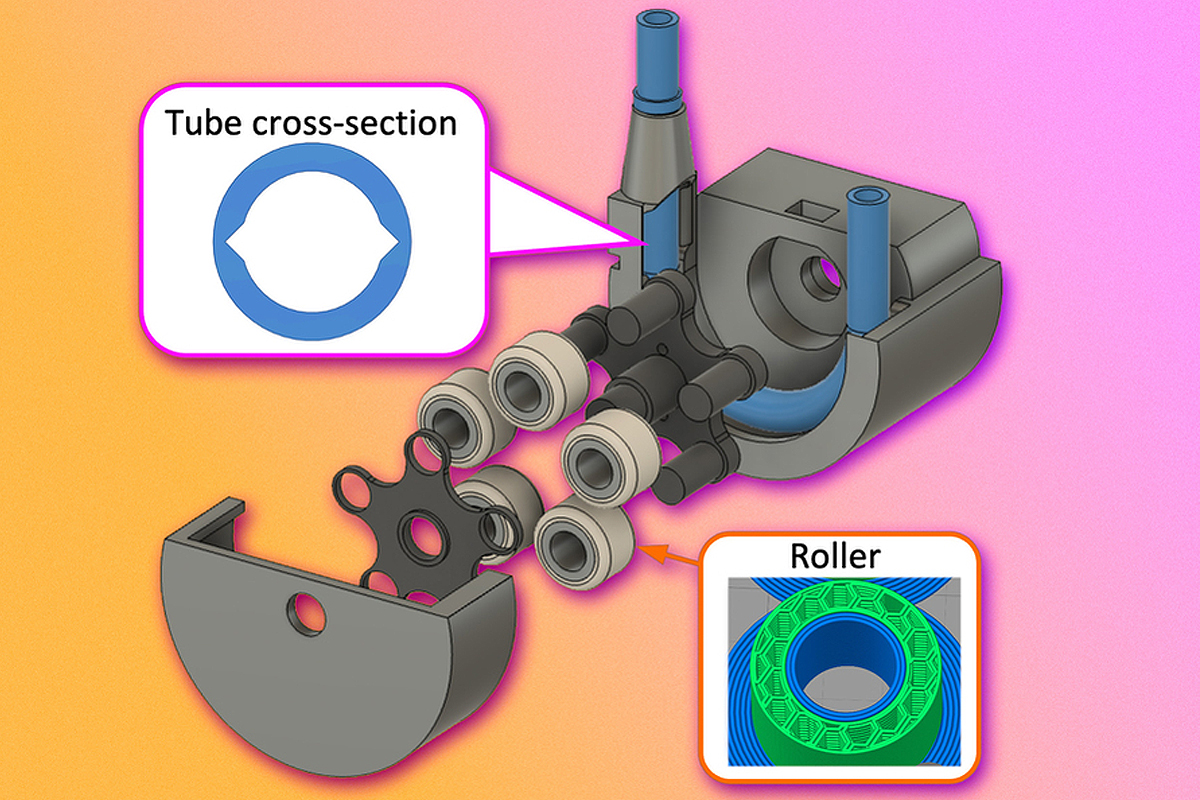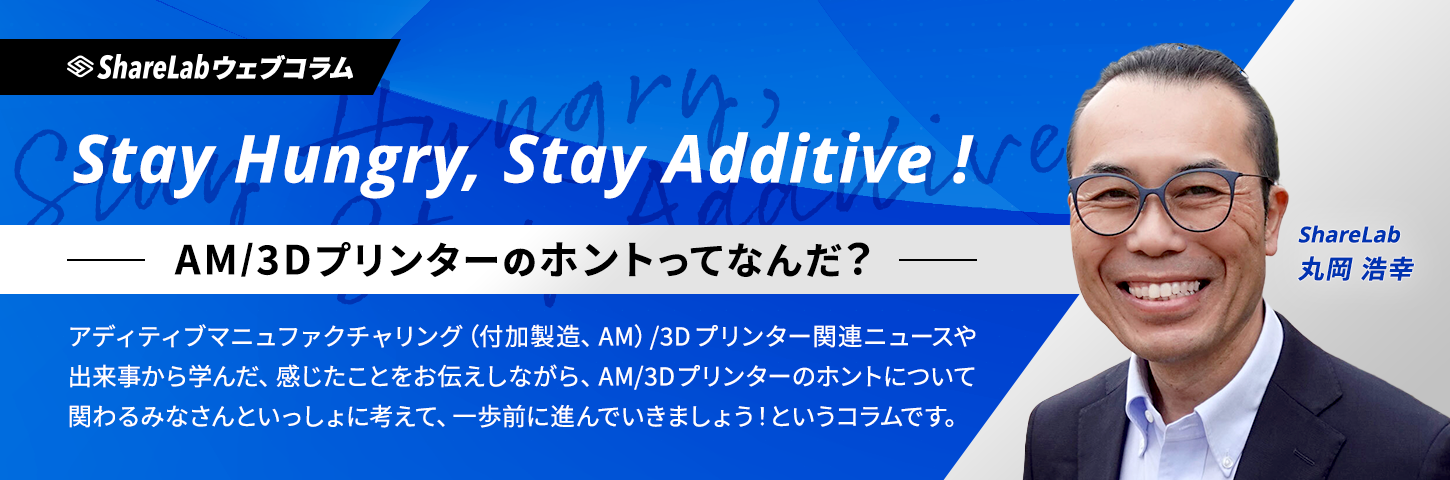
梅雨はどこに?
「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と𠮟られそうですが、早くも2025年の半分が過ぎ、後半に突入しました。いままでですとこの時期は、雨を心配して、アウトドアの旅行や遊びの予定はあまり入れなかったのですが、大した雨も降らず梅雨が明けてしまい、それなら予定を入れておくんだったと思う一方、水不足や農作物への影響も心配になります。5月ごろの予報だと梅雨入り、梅雨明け、降水量も平年並みという記事を見ましたが、これだけ観測やシミュレーション技術が発達しても、これほど梅雨が短いことは予測できなかったというのは良しとして、先のことはいろいろな可能性を想定して、手を打っておくことはあらためて大事だなと思いました。
AMとは「てんかざい」
昨日見た、アメリカとの自動車関税交渉のニュースの中で、自動車部品メーカー企業の経営層の方が、「どうなるかわからないので困った」というコメントをされていました。「先行きが見通せないので、積極的な新製品開発や投資を様子見する、控える」ようなコメントはこれまでも何度も聞いてきた気がしますし、企業経営者は事業と従業員を守らなければならないので、当然そうなると思います。一方、海外の国や企業では、関税はかかる前提で次の調達先や売り先を探したり、国内回帰をしたりする動きが活発になっているようにも見え、AM関連ニュースでも、そのための人材育成、研究開発、投資に関係する動きが増えているようです。
そのような中、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)のJohn Hart教授のお話をネットで聞く機会があり、とても参考になりました。Hart教授はメカニカルエンジニアリング分野が専門で、AM分野でも著名で、金属3Dプリンターメーカー Desktop Metal社創業メンバーでもあり、私も受講したことのあるeラーニング講座「MIT xPRO Additive Manufacturing for Innovative Design and Production」の主講師もされています。しかし教授はAM専門家ではなく、あくまで製造生産性の向上と、質の高い製造業の雇用創出を目指す研究者であり、製造教育者であり、かつ実際に複数企業の起業家でもある視点からの話は、説得力がありました。
その話の中で、「AMの現状は?」という質問に対し、MIT内部と産業の両面から見解を述べられ、MIT内部では、広い部門でAMはイノベーションと研究の推進に欠かせないものであり、産業では、製造技術の可能性を拡げ、新製品の生産を可能にする技術であるとの主旨でした。また、よくある質問で、「AMは製造のメインフレームになるのか?いつか?」に対し、「そもそもメインフレームとは?」と返されたあとで、それが大量生産用に多量の台数が使われるということであれば、それはAMだけでなく、プロセス全体で解決すべき課題が多くあるとの回答でした。
私の勝手な解釈ですが、AMは学生教育を含めた革新技術研究開発を推進させる火薬そのものではなく、「点火材」のような役割として既に欠かせないものであり、産業界においては、例えるなら金属材料としての「鉄」は主役であっても、それだけで出来る範囲は限られ、それにほんの微量でも加えることで強度、硬さ、靭性、耐食性、耐熱性など、様々な特性を向上させ、用途範囲を広げられる「添加元素(材)」のような役割がAMであるということだと思います。言い換えると、教育研究でも、産業でも、メインフレームにはならないけれども、拡げるためには欠かせないのがAMなのでしょう。
ふと気になって調べてみると、紙の雑誌や本の国内の出版市場規模は、スマートフォンの急速普及が始まった1996年ころに下がり始め、年々下がり続けているのですが、電子書籍はコミックを中心に急速に増えてはいるものの、出版全体からすると電子はまだ約3割程度で、かつ出版市場規模は日本の人口減少を加味すれば微減程度のようです。多くの情報が電子化されて数十年になるのに、未だ紙は電子に置き換わっておらず、寧ろ電子を「てんかざい」としてうまく使うことで出版産業は規模を保ち、再成長する可能性すらあることは、製造全体とAMの関係に似ているのではないでしょうか?
ちなみにサムネイルの画像は「可能性を拡げるイメージをコミック風に」と頼んで生成AIさんに作っていただきました。私には到底描けませんし、生成AIは紙と電子化とは違う普及をするかもしれませんが、「てんかざい」程度に使うのが当面は良さそうです。
ShareLabニュースにもう一言
これは海外のニュースで、かつ特にインパクトがあるように見えないニュースですが、AMで製造するにはプロセス全体の構築と標準化された品質管理を続けることが必要ですが、既に国際工業規格もあり、その規格に基づいた認証システムやサービスもありました。でも今回はアメリカの大手製造企業が25社も関わり(競合もいる)、ユーザーの立場で協力し、AM特有規格以外の既存周辺規格も含めた、品質管理認証プログラムを作ったという点に驚きました。これは、AM製造品質管理システムを必要とする企業が多いこと、自前、1社だけで作ることは難しいことも示していますが、航空機メーカーなど、厳しい品質管理システムを実際運用している企業が作った点でも、汎用性、実効性が高いのではと期待しています。
AMで手術計画、練習、教育実習用の骨、欠陥、臓器の模型を作る事例は昔から多数ありますし、歴史をたどれば初めはカタチだけ出来てもすごく、価値もあったのですが、プリンター、材料、ソフトウェアの進化と共に、より生体に近く、複雑なモデルが出来るようになったことに加え、動物や遺体が使いにくくなったり、入手しづらくなったり、結果コストも上がっていると想像でき、そうなるとこのようなモデルは以前より需要も高く、価値も高まっている背景がありそうです。もちろんプリンターや材料もすごいのですが、とにもかくにもCTデータが基になっていても、3Dプリントできる3Dデータにすることと仕上げることは至難の業で、日南社がこれまで積み上げた技術と技能の結晶であり、AMが製造やビジネスの可能性を拡げている例だと思いました。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!