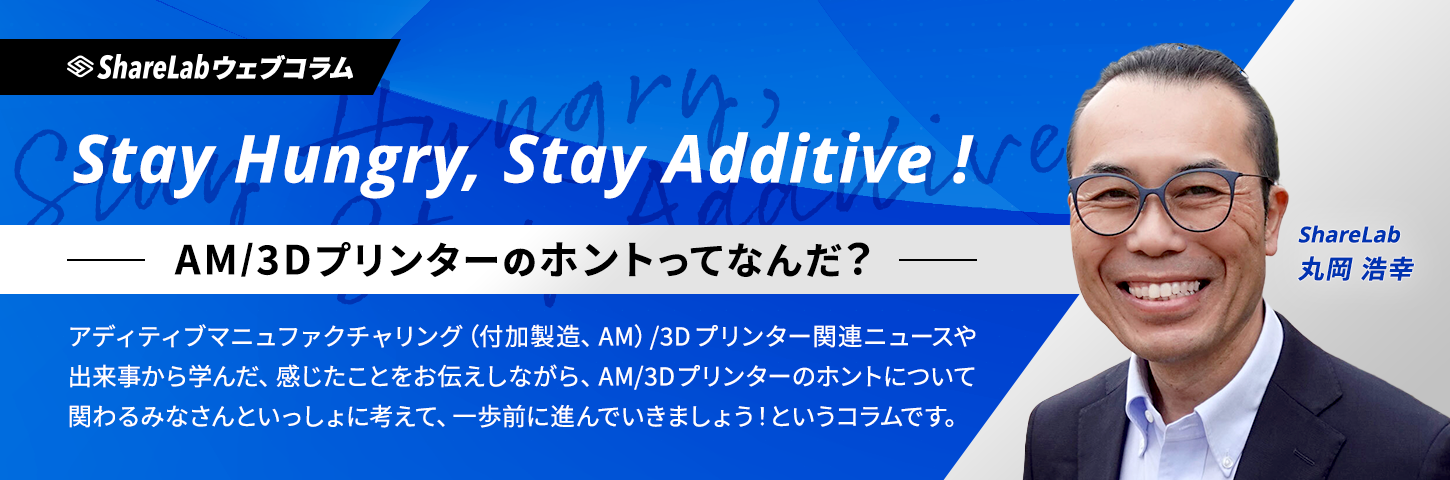
「暑い」と「熱い」
毎年恒例の梅雨の時期となりました。今年はいつもより突然梅雨入りした感じで、急に雨や曇りがちな天気が続き、長袖か半袖か迷う週があったと思ったら、今週はまた突然真夏のような暑さがやってきました。また月末にかけて梅雨の天気に戻りそうな予報ですが、お米や野菜の作況にも影響が出ないかと心配もしつつ、それより人間の方が先にダメージを受けてしまいそうです。報道でも「猛暑日」とか「酷暑」という言葉が良く聞かれ、気候の「あつい」の漢字は「暑い」ですが、ここ数日東京を昼間歩くと、日差しも、地面の照り返しも「熱い」の方が実感には近い感じがしています。今回はその「熱い」についての話題です。
Japan RepRap Festival 2025の熱さ
ShareLabのイベントページでもお知らせしてきましたが、「Japan RepRap Festival 2025 」が2025年6月14-15日に東京で開催され、ShareLabも協賛参加し、私は15日の午後だけでしたが、参加してきました。詳しい報告は衛藤記者の報告記事 愛好家の熱気が示す業務用 3D プリンター業界への処方箋~Japan RepRap Festival 2025 を参照してください。
「RepRap」と聞いて、懐かしいと感じる人が私以外の読者の中にもおられるかと思いますが、イギリスの大学の研究者 Adrian Bowyer 氏が開発した3Dプリンターをネット上で公開したのが2004年とのことで、もう20年以上たったことになります。これは当時高額で大型の3Dプリンターしか無かった時代に、作り方や部品形状もすべて一般公開し、組み立てた3Dプリンターで次の3Dプリンターの部品を作る「オープンソース」と「自己増殖(RepRapはReplicating Rapid-prototyperの短縮)」という、当時は斬新なコンセプトで、私も衝撃を受けたことを思い出します。
その後「CupcakeCNC」や「Makerbot」など派生キット製品も続々出てきて、世界的なブームになったと思います。その後2012年出版の「Makers」から起きた次の3Dプリンターブームを経て、現在まで続く大きなユーザーコミュニティになっているようです。
今回のイベント会場では、3Dプリンターブーム以来、久しぶりに熱気や「新しいモノと人との出会い」を楽しめましたが、展示された装置や作品はすごく進化していて、驚きました。また恥ずかしながら会場で初めて知りましたが、RepRapコミュニティでは世界的に「MakerChip」というモノが広まっています。カジノなどで使われるチップやトークンと似ていて、直径40mm、厚さ3~3.5mmを守って各自が自由にデザイン、設計、3Dプリントし、交換し合って楽しむものだそうです。ShareLabのブースでもたくさん交換してもらいました。

どれも個性的、素晴らしいデザインで、かつ最近のデスクトップMEXプリンターの多色化や精細度の進化もよくわかりましたし、もちろんこのようなプリント用3Dデータとツールパスを容易に作れる、またネット上でノウハウ含めてユーザーどうしが共有、進化させていることもすごいことだと思いました。
帰りのモノレールで知り合った参加者から頂いたチップは、スクリューキャップ構造で、中に植物の種が入っているという凝りようで、この厚さの中で作った発想、3D設計技術、造形技術の高さには、あらためて「好き」が生むエネルギーと熱量に感動するとともに、ユーザーの熱量が他のユーザーも、メーカーもお互い高めあう世界が、RepRapコミュニティには出来ているのではと考えながら帰りました。
AMを進化させる「ユーザーの熱量」
私もこれまで高い熱量をもってAMを活用したり、普及に取り組む個人、また組織人の方々とたくさん出会ってきましたし、逆にあまり表に出てきませんが、3Dプリンターメーカーやソフトウェアメーカーの技術者にも、高い熱量を持った方々がたくさんいました。特に海外ではユーザーとメーカー開発者が直接交流し、意見交換をしあうイベントに参加する機会が多くありました。
もちろんAMに限ったことではありませんが、ユーザーの使い方、求める成果がかなり多様、個々特殊になればなるほど、またユーザーの熱量が高いほどメーカーの熱量も高まりますし、工法、製品は改良進化も速いように思います。ただし偏見かもしれませんが、日本では「お客様は神様」的な傾向が残っていて、「ユーザーがいちいち言わなくても満足するものを作るのがメーカー」「ユーザーの要望や不満は、他のユーザーに知られたくない、広まると困る」「ユーザーは不満を伝えれば、改善するのはメーカーの役目」というような考えがあるのも事実でしょう。
しかしユーザーもメーカーもお互い熱意と敬意をもって要望を伝えあい、協働で進化させることは、メーカーの国内外問わず、特に産業用AMの進化に重要ではないでしょうか。
ShareLabニュースにもう一言
最近はこのように、メーカー主催であってもメーカーからの一方通行な情報提供より、ユーザーが話す、ユーザーどうしが交流するというイベントが増える傾向にあり、このイベントのように、積極的に成功、失敗や苦労も含め話してくださるユーザーが増え、とても良いことだと思います。特にこれからの日本のAMはユーザーが今にも増して主役、けん引役となっていくべきだと思います。
ShareLabではこれまでも、あまり知られないAMユーザーの取材やインタビューの記事を数多く届けてきました。この記事も、1件の特定の企業のAMの話ですが、日本全体の課題である中小製造企業の活性化、事業継承などの点で、多くの方の参考になる内容だと思います。
一方、美崎工場長のように、AM導入前からAMへの高い期待や熱意があったわけではなく、むしろ初めは懐疑的、否定的だったのが、とにかく使い始め、小さな成果が広がることで少しづつ前向きに、熱意も高まっていったことが伝わり、どうやらこのパターンの方が、うまく、永くAMを活用されているユーザーに多いような気がします。
ではまた次回。Stay Hungry, Stay Additive!






